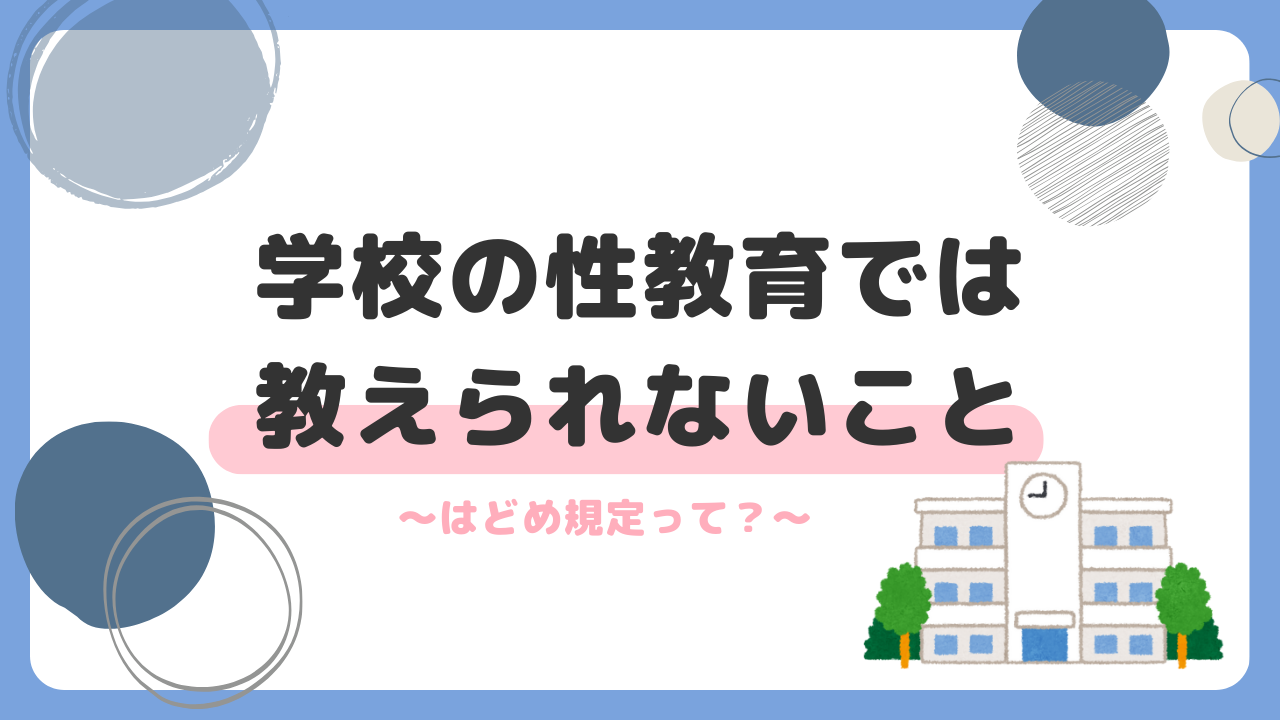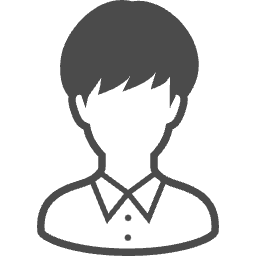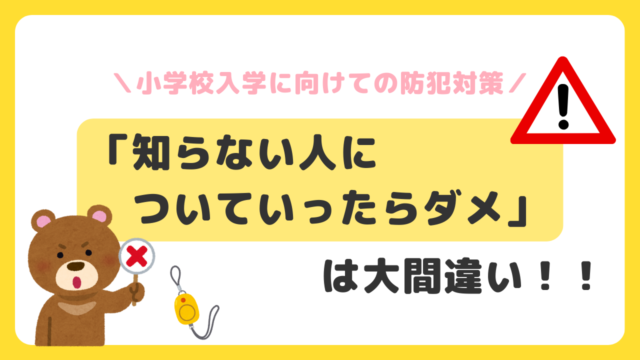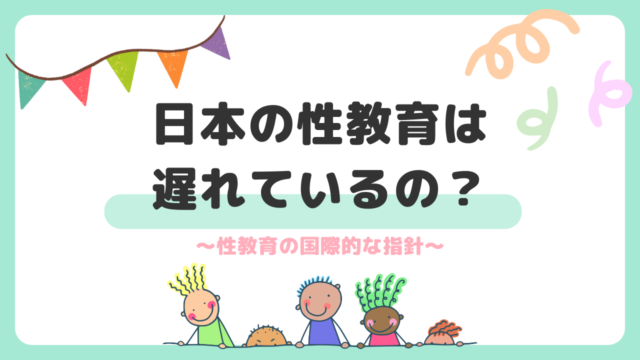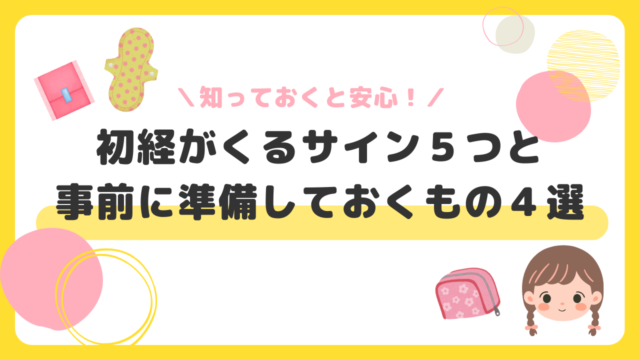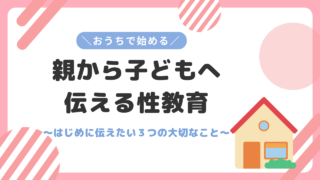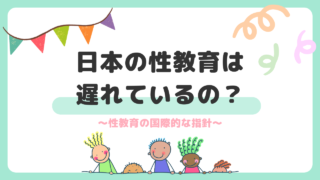性教育は『いのち・からだ・健康』の学問であり、世界的には【性=人権】という視点で幅広く学ぶことが推奨されています。
性交や避妊、性感染症などは性教育の中のほんの一部でしかないとわかっていても
やっぱりそこが一番心配。
性交や避妊についても親から伝えなくちゃいけないの?
学校にお任せしたらいいんじゃない?
そんな風に思っている方もいるかもしれません。
学校での性教育の現状についてお伝えしたいと思います。
学校の性教育ではこんなことを学ぶよ!
文部科学省が定める学習指導要領では、性教育に関する内容は、以下のように段階的に設定されています。
小学校3・4年生
・体の清潔
・男女の体の発育、発達
・初経と精通
・異性への関心
小学校5・6年生
・命の誕生
・感染症
中学校1・2年生
・月経と射精
・受精と妊娠
・性衝動
・異性との関わり方
・性情報の対処
中学校3年生
・性感染症(感染経路と予防)
実際の学習内容は地域や学校・先生によって大きく異なるよ!
先生によって違うとは言っても、これだけ教えてくれるなら、やっぱり学校にお任せすればいいんじゃない?
と思った方もいるかもしれません。
しかし、日本の学校での性教育には『はどめ規定』があります。
はどめ規定とは?
はどめ規定とは、日本の学校における性教育の内容を制限する文部科学省の指針です。
具体的には、
・小学校5年生の理科で「受精に至る過程は取り扱わないものとする」
・中学1年生の保健体育で「受精・妊娠までを取り扱うものとし、妊娠の経過は取り扱わないものとする」
という2つのはどめ規定があり、小・中学校では性交や避妊については原則、授業では取り扱わないとされています。
文部科学省は「はどめ規定」について、「全ての子どもに共通に指導すべき事項ではないという意味であり、学校が必要と判断する場合や個々の生徒に対応して教えることは可能だ」と説明していますが、より踏み込んだ内容の性教育はほとんど行われていないのが現状です。
踏み込んだ性教育が行われないのはなぜ?
文部科学省は、「はどめ規定は、性教育の内容を完全に制限するものではなく、あくまでも教育者の判断に基づいた柔軟な指導を可能にするもの」としていますが、はどめ規定を超えて踏み込んだ性教育を行っている学校はとても少ないのが現状です。
なぜ踏み込んだ性教育を行うことに積極的ではない学校・教員が多いのか…
それは、過去に踏み込んだ性教育を行った学校の校長、教職員が授業内容が不適切であったとバッシングを受け、教育委員会から厳重注意・処分を受けた事例があったことが大きく影響しています。
この出来事は、日本の性教育の在り方に長期的な影響を与え、現在でも性教育の内容や方法について慎重な姿勢が続いているのです。
子ども達はどこで性の情報を得るの?
家庭は性の話はできる雰囲気ではない。
学校の性教育では、一番知りたいことは教えてもらえない。
正しい性の知識を教えてもらう機会のない子ども達は、どんな手段で性の情報を得ると思いますか?
多くの子どもは、インターネットや漫画・先輩や友達から性の情報を知ります。
ネット上にある性の情報は正しい?
現代は幼い頃からインターネットが身近にあります。
インターネットはとても便利で、私たちの生活に必要不可欠なものになりましたが、ネット上には正しい情報だけではなく、間違った情報もたくさんあります。
しかし、正しい性の知識がなければ、ネット上にある情報が誤った情報であっても気づくことができません。
・安全日は避妊しなくて大丈夫
・女性の「嫌」「やめて」は喜んでいる証拠
・Hの後、コーラで性器を洗えば避妊しなくても妊娠しない
そんな間違った情報を、正しいと思っている子どもが実際にいるのです。
彼女が妊娠して、気付いた時には人工妊娠中絶をできる時期が過ぎていた高校生の男の子は…
アダルトコンテンツでは避妊をしないのが当たり前。
今まで避妊の必要性や方法、妊娠の過程について正しく教えてくれる人はいなかった。
教えてほしかった…
と泣きながら話していました。
自分を大切にするために、自分の大切な人を大切にするために、おうちでの性教育を通して子ども達が幸せな人生を送るための土台を作っていくことが必要です。
まとめ
学校での性教育には「はどめ規定」があり、十分な性教育は行うことが難しい現状についてお伝えしました。
現在の日本では、学校教育だけで正しい性の知識を学ぶことはできません。
性交や避妊、性感染症は性教育のほんの一部であり、今現在そのことについては家庭で触れることに抵抗があるという方もいると思います。
親が話しにくいと思っていることを無理に話す必要はありません。
子どもが何か困った時、不安を感じた時に「信頼できる・安心して話せる」信頼関係を築けるよう、幼い頃からコミュニケーションを大切にし、子どもの声に耳を傾け、「大切な存在だよ」と伝え続けることがとても大切です。